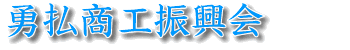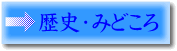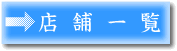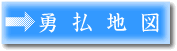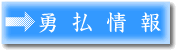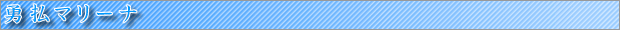
 ウォーターフロントを身近なものにするため「水辺のレクリエーション施設を港湾空間に」という市民、関係団体からの声や、近年の海洋性レクリエーション需要に対応するため、平成元年に「勇払情報」事業に着手し、平成12年完成いたしました。船だまりは、プレジャーボートや有漁船等を収容いたします。
詳細なマリーナ情報は、ホームページにて。
ウォーターフロントを身近なものにするため「水辺のレクリエーション施設を港湾空間に」という市民、関係団体からの声や、近年の海洋性レクリエーション需要に対応するため、平成元年に「勇払情報」事業に着手し、平成12年完成いたしました。船だまりは、プレジャーボートや有漁船等を収容いたします。
詳細なマリーナ情報は、ホームページにて。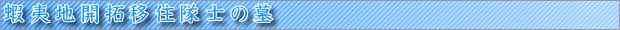
 1800年蝦夷地の警備と開拓のため移住した八王子千人同心関係、4基9名、勇武津会所関係の医師、役人、通詞とその家族7期8名、場所請負人、山田屋関係1基6名、合計18期29名が祭られています。
例年8月20日には慰霊祭が行われています。
1800年蝦夷地の警備と開拓のため移住した八王子千人同心関係、4基9名、勇武津会所関係の医師、役人、通詞とその家族7期8名、場所請負人、山田屋関係1基6名、合計18期29名が祭られています。
例年8月20日には慰霊祭が行われています。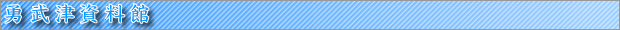
 幕末の勇武津会所を模した建物は、国産のスギ材で内外装され、土間にはカマド、板の間には囲炉裏が復元され各種の調度品が並べられています。多目的研修室には・勇武津会所・八王子千人同心・開拓使三角測量・弁天貝塚出土品・アイヌ民具や北前船関係の歴史資料が展示されています。
幕末の勇武津会所を模した建物は、国産のスギ材で内外装され、土間にはカマド、板の間には囲炉裏が復元され各種の調度品が並べられています。多目的研修室には・勇武津会所・八王子千人同心・開拓使三角測量・弁天貝塚出土品・アイヌ民具や北前船関係の歴史資料が展示されています。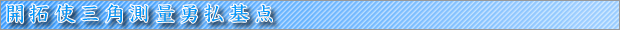
 1873年、三角測量法による地図作りに着手しました。その成果は1876年ニューヨークで「北海道測量報告」として発表されました。
北海道史上、我が国測量史上貴重な史跡として1967年3月17日、北海道指定文化財史跡として指定されました。なお、勇払基点は1962年、盛土下から胴棹のある石柱の発見によるもので、標題は苫小牧市博物館に復元展示されている。
1873年、三角測量法による地図作りに着手しました。その成果は1876年ニューヨークで「北海道測量報告」として発表されました。
北海道史上、我が国測量史上貴重な史跡として1967年3月17日、北海道指定文化財史跡として指定されました。なお、勇払基点は1962年、盛土下から胴棹のある石柱の発見によるもので、標題は苫小牧市博物館に復元展示されている。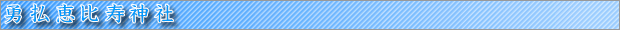
 シコツ場所が成立したころに建立された弁天社に由来する。明治以降、厳島神社。事代主社、蛭子神社など名称を経て、1952年、現在の社名となった。同社には、絵馬・扁額・手水鉢など奉納品21点が市指定文化財として保存されています。
シコツ場所が成立したころに建立された弁天社に由来する。明治以降、厳島神社。事代主社、蛭子神社など名称を経て、1952年、現在の社名となった。同社には、絵馬・扁額・手水鉢など奉納品21点が市指定文化財として保存されています。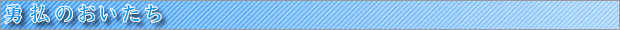
勇払の地名は、アイヌ語の「イプツ。それの入り口」という川の名で、 内陸への重要な入り口という意味があり、その初期の勇払の役割は周辺地域の生産物の集荷、積み出し等、交易の要衝であった。
その後、対外的にはロシアとの協会の取り締まり、対内的には放任していた交易と行政の弊害を改める目的で、寛政11年(1799年)東蝦夷地を幕府の直轄地として、新たに勇払場所として整備された。
商品取扱所の運上屋は会所と改め、ここに役人が詰めて交易の公正を計り、付近には倉庫や作業所、通行人や馬車の継立等のための旅宿所などを整え、寛政12年(1800年)八王子千人同心が配備され、警備のほか、会所用務の一部もこなした。
明治2年(1869年)北海道開拓使の勇払役所開設(蝦夷地から北海道へ名称変更)
明治6年(1873年)役所を苫細村(現苫小牧市)へ移転する
明治25年(1892年)苫小牧駅ができる
明治43年(1910年)王子製紙苫小牧工場操業開始
昭和18年(1943年)大日本再生製紙(現日本製紙)勇払工場操業開始
昭和26年(1951年)日本初の大規模な掘込式苫小牧港の起工式
その後、対外的にはロシアとの協会の取り締まり、対内的には放任していた交易と行政の弊害を改める目的で、寛政11年(1799年)東蝦夷地を幕府の直轄地として、新たに勇払場所として整備された。
商品取扱所の運上屋は会所と改め、ここに役人が詰めて交易の公正を計り、付近には倉庫や作業所、通行人や馬車の継立等のための旅宿所などを整え、寛政12年(1800年)八王子千人同心が配備され、警備のほか、会所用務の一部もこなした。
明治2年(1869年)北海道開拓使の勇払役所開設(蝦夷地から北海道へ名称変更)
明治6年(1873年)役所を苫細村(現苫小牧市)へ移転する
明治25年(1892年)苫小牧駅ができる
明治43年(1910年)王子製紙苫小牧工場操業開始
昭和18年(1943年)大日本再生製紙(現日本製紙)勇払工場操業開始
昭和26年(1951年)日本初の大規模な掘込式苫小牧港の起工式
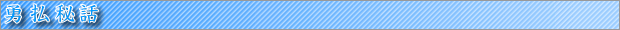
(1857・1863年)高知藩による北海道視察の情報が坂本龍馬に伝えられ、勇払・千歳を中心とした蝦夷地移住開拓計画があったそうな。
もしかしたら勇払の浜に龍馬が立ったのかも・・・
もしかしたら勇払の浜に龍馬が立ったのかも・・・